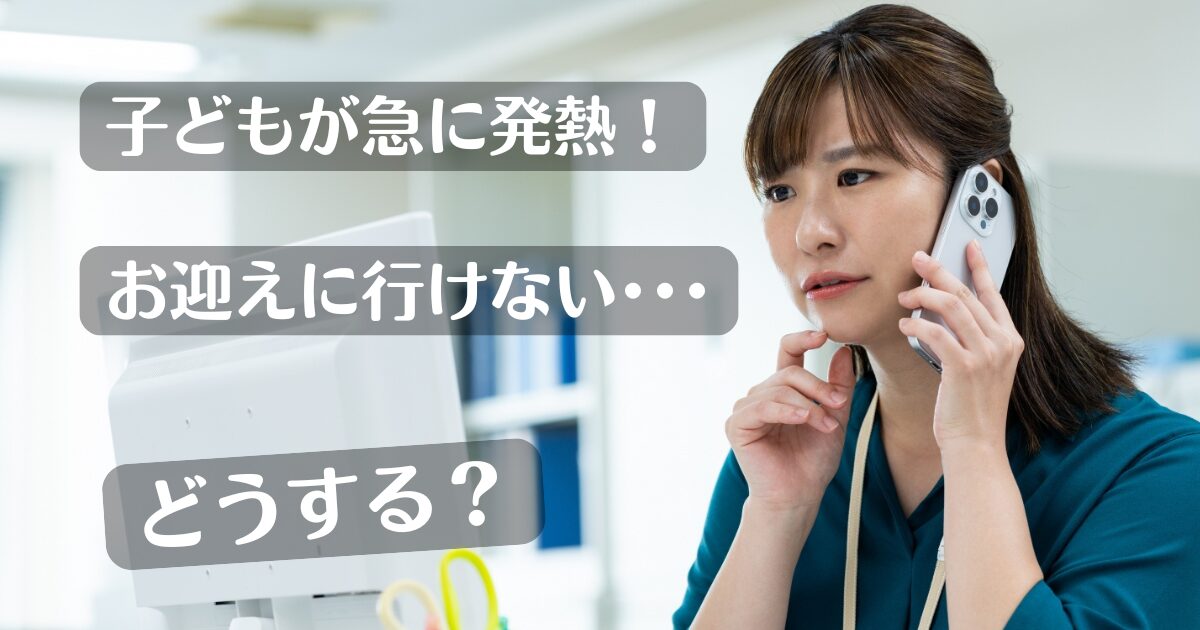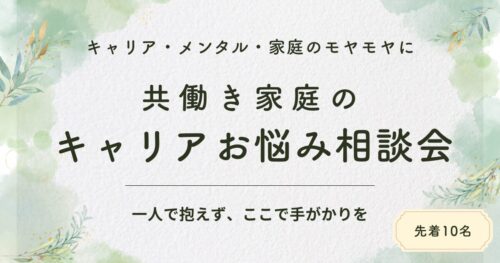仕事が忙しい時に限って、子供が熱を出してお迎え要請・・・
共働きで子育て中のママパパにとって、多くの方が経験する「あるある」ではないでしょうか?
共働きの我が家も、何度もこの状況に直面してきました。
そのたびに、「どうしよう…」と夫婦で慌てふためき、バタバタと対応。しかし、繰り返すうちに、効果的な対策や乗り切るためのノウハウを身につけることができました。
この記事では、2児のパパのキャリアコンサルタントが、我が家のリアルな体験も交えて、子どもの急な体調不良にどう備え、どう乗り越えるかをお届けします。
夫婦で話し合い連携を強化する「家庭内での備え」
朝、子どもが熱を出していることに気づいた瞬間、夫婦で「どうする?」「誰が休む?」とパニックになった経験はありませんか?
このような混乱を招かないように、事前に夫婦で話し合って対策を共有しておきましょう。
役割分担ルールを事前に決めておく
キャリアコンサルタントとして多くの共働き家庭の悩みを聞く中で、「夫婦間のすれ違い」が大きなストレス源になっているケースをよく目にします。子どもの体調不良時も例外ではありません。
そこで、子どもが急に体調を崩した際に備えて、夫婦同士で話し合い、役割を決めておきましょう。
我が家では、「基本的には妻が対応し、妻が難しい場合は夫が対応する」といったように、大まかでもルールを決めています。
こうしたルールがあるだけで、緊急時でも「誰が動くべきか」が明確になり、「どうする?どうする?!」という混乱をグッと減らすことができます。
もちろん、状況に応じて柔軟に対応できるよう、日頃からコミュニケーションをとっておくのも大切なポイントです。
絶対に外せない予定を日頃から共有する
仕事の締め切りや重要な会議、出張など「この日はどうしても動けない」という予定は、夫婦間で必ず共有しておきましょう。
我が家では、Googleカレンダーやタイムツリーなどの共有スケジュールアプリを活用しています。
お互いのスケジュールが「見える化」されていると、どちらが優先的に対応すべきかがすぐに判断できます。
これは、お互いへの気遣いにも繋がり、円滑な夫婦関係を築く上でも非常に効果的だと感じています。
テレワークを最大限に活用する
会社が在宅勤務を許可している場合、テレワークは共働き家庭にとって非常に強力な味方になります。
我が家の場合、妻が在宅勤務中心で、会社の規定で一時的に仕事を中断できるため、子どもの体調不良時に病院に付き添ったり、子どもの様子を確認しながら最低限の業務をこなしたりした経験があります。
キャリアの観点からも、テレワークは仕事と育児の両立を可能にする柔軟な働き方の一つです。
パートナーの仕事を外せない日があらかじめ分かっている場合は、事前に「この日は自分が家で対応できるようにしておこう」と調整しておくことで、いざという時の精神的なゆとりが生まれます。
家庭だけでなく職場も味方に!子どもの急な体調不良に備える「頼れる連携術」
夫婦間の協力だけでは限界があるのも事実です。そんな時に頼りになるのが、外部のサポートです。日頃からの備えが、いざという時の大きな安心材料になります。
かかりつけ医との信頼関係を築いておく
子どもの急な体調不良時に安心して相談できる医療機関の存在は、共働き家庭にとって非常に心強い味方です。
我が家では、ママパパ友から評判の良い小児科を事前にリサーチしておき、何かあったらその小児科に通うようにしています。
病気でなくても、予防接種や乳幼児健診などで定期的に訪れ、医師や看護師さんと日頃から信頼関係を築くようにしています。
そうしておくと、いざ緊急時でも子どもの様子をスムーズに伝えられ、必要な診断書の発行を含めた適切な対応がスムーズになりやすいと実感しています。
職場や上司と円滑なコミュニケーションを築く
子どもの体調不良は、親がどんなに気を付けていても防ぎきれないもの。
仕事中にやむを得ず遅刻や早退が必要になる場面は、共働き家庭では避けて通れません。
だからこそ、職場の理解を得ておくことが最大のリスクヘッジにつながります。
そのためには、日頃から上司や同僚とのコミュニケーションを築いておくことが大切です。
たとえば、ランチタイムや雑談の中で、家庭や子どもの事情や近況についてさりげなく共有しておきます。
そうすることで、いざというときの協力が得られやすくなります。
価値観の異なる可能性のある職場や上司であっても、関係性を積み重ねていくことは、長期的なキャリアを守るうえでも重要な備えになります。
外部サービスでの対応も視野に入れる
子どもの急な体調不良時には、病児保育や病児に対応可能なベビーシッターのような外部サービスを活用するのも一つの方法です。
病児保育は看護師や保育士が常駐し、体調管理を任せられる安心感があります。
また、病児対応シッターは、自宅での看病を希望するのに適しており、慣れた環境で子どもが安心して過ごせるのが魅力です。
いずれも利用には事前登録や診断書、サービスごとの条件確認が必要です。シッターの利用については、事前に面談をしておくと安心です。
いますぐ使わなくても「選択肢がある」ということが心の余裕につながりますので、関心のある方は早めに準備しておきましょう。
親として持っておきたい「心構え」
すべてを完璧にこなそうとすると、思いがけない出来事に心が折れてしまうこともあります。
子どもの不調に向き合うときこそ、親が自分を責めずにいられるよう、心の準備をしておくことも大切です。
「子どもの体調不良は仕方ない」と割り切る
子どもの体調不良による遅刻や早退、欠勤が続くと、「また休んでしまった…」「周りに迷惑をかけて申し訳ない…」と罪悪感を抱くこともあるでしょう。
しかし、「体調不良は仕方ない」と割り切る視点も必要です。
職場のことを気にするあまり、自分を責めすぎてしまうのは、メンタル不調につながります。
まずは、子どもの看病とご自身の心の安定を優先しましょう。
実際、キャリア相談に来られる方の中には、無理を続けた結果、心身のバランスを崩してしまう方も少なくありません。
自分を追い込みすぎないことは、長く働き続けるうえでも大切な「備え」になるのです。
どうしても理解が得られない職場なら、環境を見直すことも
職場の理解が得られないまま無理を続けると、心も体も疲れてしまいます。
長く働き続けるためには、子育てに理解のある職場に身を置くことも、前向きなキャリア選択の一つです。
これは決して「逃げ」ではありません。自分と家族のための前向きなキャリア選択です。
もし、現状に限界を感じているなら、転職を検討する前にキャリアカウンセリングを受けるのも一つの方法です。
本記事の著者が提供している共働き家庭のキャリア相談では、転職を前提としない人生全体の視点からのキャリア相談を行っています。
家庭・職場・心を整え、急なトラブルにも冷静に対応
子どもの急な体調不良は、共働き家庭にとって避けて通れない出来事です。でも、事前に備えをしておけば、慌てることなく落ち着いて対応することができます。
夫婦での話し合いやスケジュール共有、テレワークや外部サービスの活用、かかりつけ医や職場との関係づくりなど、できる備えはたくさんあります。
大切なのは「いつか起きるかもしれないこと」に対して、心と環境の両面から準備しておくことです。完璧でなくても、「選択肢を持っている」というだけで、気持ちはぐっと軽くなります。
いざというときに自分を責めすぎず、子どもにも自分にもやさしい選択ができるように、少しずつ備えていきましょう。