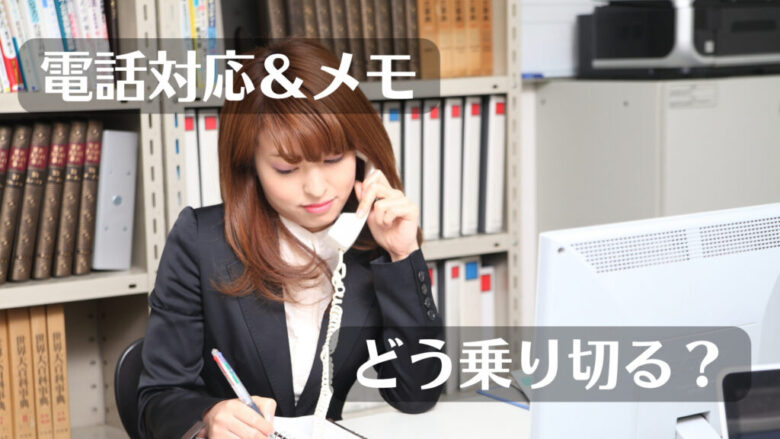仕事中、電話が鳴ったらすぐに受話器を取り、相手の名前や用件を聞きながらメモを取り、取次相手にそのメモを渡す。
仕事をされてきた方の多くは、このような電話取次ぎ対応の経験があるかと思います。
しかし、ある程度の経験があっても、この対応が苦手な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
かつての私も、聞きながらメモを取るのが大の苦手でした。
新入社員研修などでビジネスマナーの講師から、電話の内容は全文正確にメモを取るよう教わったものの、実際にやってみるとパニックに。
聞くことに集中すると手が止まり、書くことに集中すると話を聞き逃す…。
そして、電話終了後、紙に書いたメモと思われる単語を見返しても、自分でも解読不能な単語の羅列。
その単語を、あーでもない、こーでもない、と文脈が通るよう、つなげていました。
特に上司宛やクレームの電話となると、失敗は許されないという心理が働き、緊張と不安がMAXに。
失敗した時のダメージは大きく、落ち込んでしまったことも結構ありました。
そしてそれが続くと、失敗の怖さから、電話を取りたくなくなってしまいます。
かつて私は、電話が鳴ったと同時に、取引先の会社に電話をかけるふりをしたり、受話器を取る姿勢を見せつつも、わざと遅れて反応して、他の人に電話を取らせたりしたことがありました(今だから言える笑)。
そんな小手先の演技を思い付くくらいなら、電話対応&メモスキルを身につけたほうが気が楽です。
そこで今回は、全文メモを取るのが苦手な方、マルチタスクが苦手な方のために、困難を乗り越えるためのメモの取り方のコツについてご紹介します。
この記事では、電話メモが苦手な方やマルチタスクが苦手な方に向けて、実践的な「伝言メモの取り方」のコツを紹介します。
著者プロフィール
キャリアリカバー代表。国家資格キャリアコンサルタント(登録番号16062528)
企業・教育機関・医療機関を対象に、キャリアコンサルティングや研修を行うほか、
個人向けには、キャリアカウンセリングやキャリアプログラムを提供。
現在は心療内科クリニックや大学で「キャリアデザイン」の講師として活動、
東京都健康長寿医療センター研究所では、キャリアコンサルタントとして孤立・孤独の予防の研究に従事。
これまでに6,600回以上のキャリア相談と700回以上の研修・セミナーを実施。
男性育休6か月や家事育児10年以上の経験、自ら転職7回、ニート2年、事業縮小による解雇経験もあり、
実体験に基づいた共働き家庭のキャリア支援やレジリエンスも得意です。
自分に合った「伝言メモ」を準備する

聞きながらメモが取れない理由を整理する
まずは「なぜ自分はメモが苦手なのか」を整理してみましょう。
たとえば、経験不足、マルチタスクが苦手、注意散漫、発達課題など、原因は人によってさまざまです。
しかし、苦手だから、マルチタスクができないから、発達障害だから無理と決めつけてしまうのは、大変もったいないことです。
実際、私が心療内科クリニックで行っているキャリア支援でも、患者さんから「発達特性があって、電話中にメモを取るのが難しいんです…」といった相談を受けます。
でも、そうした方の多くは「自分に合ったメモの取り方」を知らなかっただけ。やり方を一緒に見つけて、練習を重ねていく中で、「あ、自分でもできるかも」と手応えをつかんでいかれます。
ご自身の特性や持ち味、その対策を詳しく知りたい方は、自分の特性や強みを把握できるキャリアカウンセリングのサービスを活用してみるのも一つの方法です。
いずれにしても、自分のやりやすい方法を探すことが、克服に向けた第一歩です。
自分に合ったメモ媒体を選ぶ
問題点が把握できたら、それを踏まえてメモをするための材料を選びましょう。
メモの材料として考えられるもの
- メモ用紙
- PC(word・テキストメモ・outlookなど)
- スマートフォン
- メモパッド・ペンタブレット
- ボイスレコーダー
紙媒体以外にもメモを取るツールがありますが、最も多くの方が使われているのはメモ用紙かと思います。
メモ用紙は、裏紙を使う方もいれば、会社が用意した日時や用件、電話番号などの項目があらかじめ印字されたテンプレート付きメモ用紙を使っている方もいるでしょう。
テンプレート付きメモ用紙は、必要事項をテンプレートの項目に沿って埋めていくことができるので、相性が良ければ便利なツールです。
しかし、私のように、テンプレートの項目を埋めることに気を取られてしまい、逆に上手くメモを取れなかったり、相手の話を聞きそびれたり人もいるのではないでしょうか。
そんな時は、通話中は白紙にメモを取り、あとでテンプレート用紙に清書する方法が有効です。
メモしやすい環境をつくる
電話が鳴ってから慌ててメモ用紙を探す…あるあるですよね。
できれば、受話器を取ると同時にメモができるよう、手の届くところにメモ用紙を置いておきたいものです。
しかし、他の仕事が舞い込んでしまいマルチタスク状態になってしまうと、その仕事の書類にメモ用紙が埋もれたりするなどして、いつの間にかメモ用紙がどこかにいってしまうことも。
私も以前そのような環境で電話を取ったことがあり、その時は慌てて近くに置いてある書類の裏にメモをしました。
電話を切ってその書類を見返すと、それが重要書類だったこともありました笑
机の上のメモ用紙が行方不明になってしまいがちな方は、いざという時にメモ用紙を取り出せるよう、電話の近くに設置するだけでなく、机の前面の引き出しにも入れておくとよいでしょう。
メモ用紙が定位置かつ2か所にあれば、電話が鳴る→電話を取る→机上にメモがない→机の引き出しからメモを取り出す→メモを取る、といった具合に慌てずにメモを取ることができます。
それでも、メモ用紙が近くにない状況で電話を取ってしまうこともあるかと思います。
そのような場合は、PCやスマホ、タブレットに入力する方法があります。
この場合、文字入力のために両手がふさがり、受話器を耳に挟みながら対応すること可能性が出てきます。
その際は、誤って受話器を落としたり、通話終了のボタンを押さないよう気を付けましょう。
タブレットの場合は、ペンタブレットのように手書きでメモが取れるのもあります。
タブレットであれば他の書類と混同することはないと思いますので、メモ用紙の代わりとして用意しておくのもいいかもしれません。
【Amazonで人気】書きやすいタブレットをチェック
Amazon ペンタブレット一覧さらに便利なツールとして、ボイスレコーダーもおすすめです。
特に、最新のAI技術を搭載したボイスレコーダーは、録音から文字起こしまでを自動で行ってくれるため、電話中のメモ取りが格段に楽になります。
例えば、
PLAUD NOTE
は、クリアな音質で最大30時間の連続録音が可能です。ノイズキャンセル機能も搭載しており、会議やインタビュー、電話の録音に最適です。
2024年8月現在、4.5以上のレビューがついていますので、興味のある方はチェックしてみてください。
6ヶ月で全世界5万ユーザー&12億円売り上げAIボイスレコーダー PLAUD NOTE電話で聞きながらメモを取るポイント

文章化は最後でもOK、まずはキーワードを抽出
『相手が話していることを一字一句メモを取る』先述の通り、私にとってこの作業は至難の技です。
電話相手は、必ずしも正しい文法や言葉遣いで分かりやすく伝えてくれるとは限りません。
あれこれ思い出しながら話すことで、文脈が前後したり、単語の羅列になったりすることもあるでしょう。
そのような不完全な話の内容を、てにをはを意識しながら、文章化しようとすると、やがて相手の話すスピードについていけなくなってしまいます。
それでも、先方の話にしがみつきながら、なんとか全文メモを取ろうとするのですが、メモした文字を見返してみると、自分でも解読不能なミミズ文字のオンパレード。
これでは本末転倒です。
相手の話す内容のメモが取りにくいと判明した場合、まずはキーワードだけでも抽出することをおすすめします。
キーワードが分かれば、ある程度の要点が把握できます。
流れや結論を導くときは記号をつかう
キーワードが抽出できれば、前後関係をつなげてメモします。
この時、記号を使い図式化すると分かりやすいかと思います。
私がよく使う記号は矢印です。
矢印は、結論と理由の関係を表したり、メモを渡す相手に依頼したりする際に使います。
取次相手がそばにいる場合は、速やかにつなぐ
取次相手がそばにいる場合、先方の用件を全て聞く必要はありません。
自分経由で用件を取次相手につなぐよりも、取次相手が先方から直接用件を聞いたほうが確実に伝わるからです。
特に、クレームの電話の場合は、先方の話が長くなりがちで、その話に聞き入っていると混乱する可能性が高くなります。
したがって、取次相手がそばにいる場合は、先方の社名と名前、用件のみを聞き、速やかにつなぎましょう。
緊急時等の場合は、とりあえず連絡先を聞き、折り返すことを伝える
状況によっては、相手の声が何らかの理由で聞き取りにくかったり、緊急の仕事の対応に追われていて用件が頭に入ってこなかったりすることもあるでしょう。
もちろん、顧客を優先して対応するのは当然のことですが、先方の話が長くなってしまったり、他の用事に気を取られたりするなどして、器用にメモが取れない方もいらっしゃるかと思います。
そのような余裕のない状況の場合、緊急的な手段として、とりあえず先方の社名と名前、電話番号と取次相手だけメモを取り、折り返しの電話を入れるよう伝え、取次相手に折り返しの電話をお願いするという手もあります。
電話を切る前に、社名と名前、電話番号を復唱し、しっかり確認しておきましょう。
電話対応後の伝言メモの取り方のコツ

メモしたキーワードを文章化して清書する
通話が終了したら、キーワードで書いたメモを文章化します。
この時、話し言葉を書き言葉に変換するのが苦手な方もいらっしゃるかと思います。
そんな時、カギかっこを使い相手のセリフをそのまま記入する方法もあります。
多少冗長な表現になることもありますが、相手には正確に伝わりやすいです。
取次相手へ渡す清書用メモの例
○○課長
▲▲会社◆◆様よりTEL有
「9/13(火)15時のアポイントの件、
都合が悪くなった。
→9/20(火)15時に変更してほしい」
03-××××-××××
9/12(月) 13:35 ◎◎
テンプレートのメモ用紙を活用される方は、テンプレートに沿ってメモを仕上げます。
ここで重要なのが、完璧に文章化しようとしないことです。
正確に伝えようとしすぎるあまり、作文の時間が長くなると、他の仕事に支障が出てしまいます。
そのような場合は、箇条書き+口頭による説明にする方法や、上記のように社名と人名と連絡先のみをメモする方法もあります。
どんなに忙しい場合でも、口頭のみの伝言は伝え間違いのリスクや、言った言わないなどのトラブルを生む可能性が高いので、メモを取ったうえで口頭で伝えることをおすすめします。
なお、取り次ぐたびに手で書くのが面倒な方には、付箋やメモに押すだけで
伝言メモがつくれるスタンプ
を利用されるのもおすすめです。
メモを清書したらすぐに取り次ぐ
メモを清書化する途中や清書化したメモを上司や同僚に渡す際、別の仕事が舞い込んでくることがあります。
この時、可能な限り、別の仕事に着手するのは一旦保留にして、先にメモを渡す業務を済ませてことをおすすめします。
別の仕事に着手すると、メモを渡す仕事を忘れる恐れがあり、メモの内容が急ぎの用件の場合、上司や同僚、顧客に迷惑をかけることになります。
簡単な仕事でもたくさん抱えると、後でまとめて処理する際、一つひとつ思い出しながら着手することから、逆に非効率になる可能性があります。
特にマルチタスクが苦手の方は、仕事を抱え過ぎないように気を付けましょう。
電話で聞きながらメモを取る業務はスキルアップのチャンス
様々な書籍からメモの取り方を学ぶ
メモの取り方は、一つの方法だけとは限りません。
上記でご紹介した他にもメモの取り方が紹介されている書籍を参考にしてもよいでしょう。
何冊もの本を探すのが面倒な方は、たとえば、下記のような電子書籍読み放題サービスに申し込めば、ビジネス経験豊富な様々な著者が書いた「メモの取り方」に関する書籍がまとめて読めるのでおすすめです。
KADOKAWAが提供する
BOOK☆WALKER「マンガ・雑誌読み放題」サービス
は、マンガ雑誌90誌以上や単行本30,000冊以上が月額836円(税込)または月額840円(税込)で読み放題です。
また、amazonが提供する
Kindle Unlimited
は、月額980円(税込)で幅広いジャンルの200万冊以上の本が読み放題、初めてご利用の方は30日間の無料体験がついてきます。
どちらの読み放題サービスも、メモの取り方以外にも様々なビジネスに関するノウハウ本が読めます。
月に数冊の書籍を読む方は、読み放題サービスのほうがお得になる可能性が高いので、検討してみても良いかもしれません。
電話対応&メモの仕事はたくさんのメリットがある
このように、メモの取り方は多種多様です。
様々な方々のメモの取り方を参考にして、自分の特性やスキルに合ったメモの取り方を習得すると、スムーズな電話対応につながります。
「ここまでして電話を取る必要があるのだろうか」と疑問を抱いたり、苦手意識が先行して電話を取ることを躊躇することもあるかと思います。
しかし、電話の取次ぎをたくさんすればするほど、外部や内部の方々とのコミュニケーションや用件を要約する機会が増えるため、確実にビジネススキルがアップします。
特に、新入社員や転職して間もない方々は、仕事を覚えたり人間関係を円滑に築いたりする絶好のチャンスですので、失敗を恐れつつも率先して電話を取り続けることをおすすめします。
ネガティブになりがちな電話対応業務をコミュニケーション機会を増やすチャンスと捉え、仕事の時間が有意義なものになるといいですね。
電話でのメモが苦痛な場合は、環境を変えることも一つの方法
ここまで電話中のメモ作業について説明してきましたが、もしかしたら業務そのものが苦痛でしょうがないと感じる方もいるかもしれません。
その場合、以下のことを検討してみてください。
上司に相談する
苦痛な業務から逃げ出したいあまり、別の部署への異動したいという気持ちはよくわかります。
しかし、こればかりは会社の事情もあるため、非常に難しいかもしれません。
まずは、自分の担当業務やキャパシティについての困りごとについて共有したうえで、電話のメモ作業を軽減してもらい、代わりに他の業務の担当を与えてもらえるかどうか、上司に相談してみましょう。
転職を検討する
自分で対策を講じても、上司に提案しても改善の見込みがない場合や、職場環境も変えられそうにないと感じるなら、他の職場を探すのも一つの方法です。
ただし、安易な転職はリスクが伴うため、転職で後悔したくない方は、まずは信頼できる友人や知人、第三者に相談することをおすすめします。
人材エージェントに相談する方法もありますが、転職を前提とした相談になってしまいますので、残留も視野に入れている方は、自分のキャリア人生に寄り添ってくれるキャリアカウンセラーに相談するとよいでしょう。
なお、本サイト運営のキャリアリカバーでは,、電話でメモを取るなどのマルチタスクに困っている方や、職場環境を変えて転職したいがどうしたらいいか分からない方のために、トラブルを乗り越えるためのキャリアカウンセリングを行っています。
キャリアリカバーのキャリアカウンセリングに関心のある方は、失敗や負の経験も財産に変えるキャリアカウンセリングサービスもどうぞご覧ください。