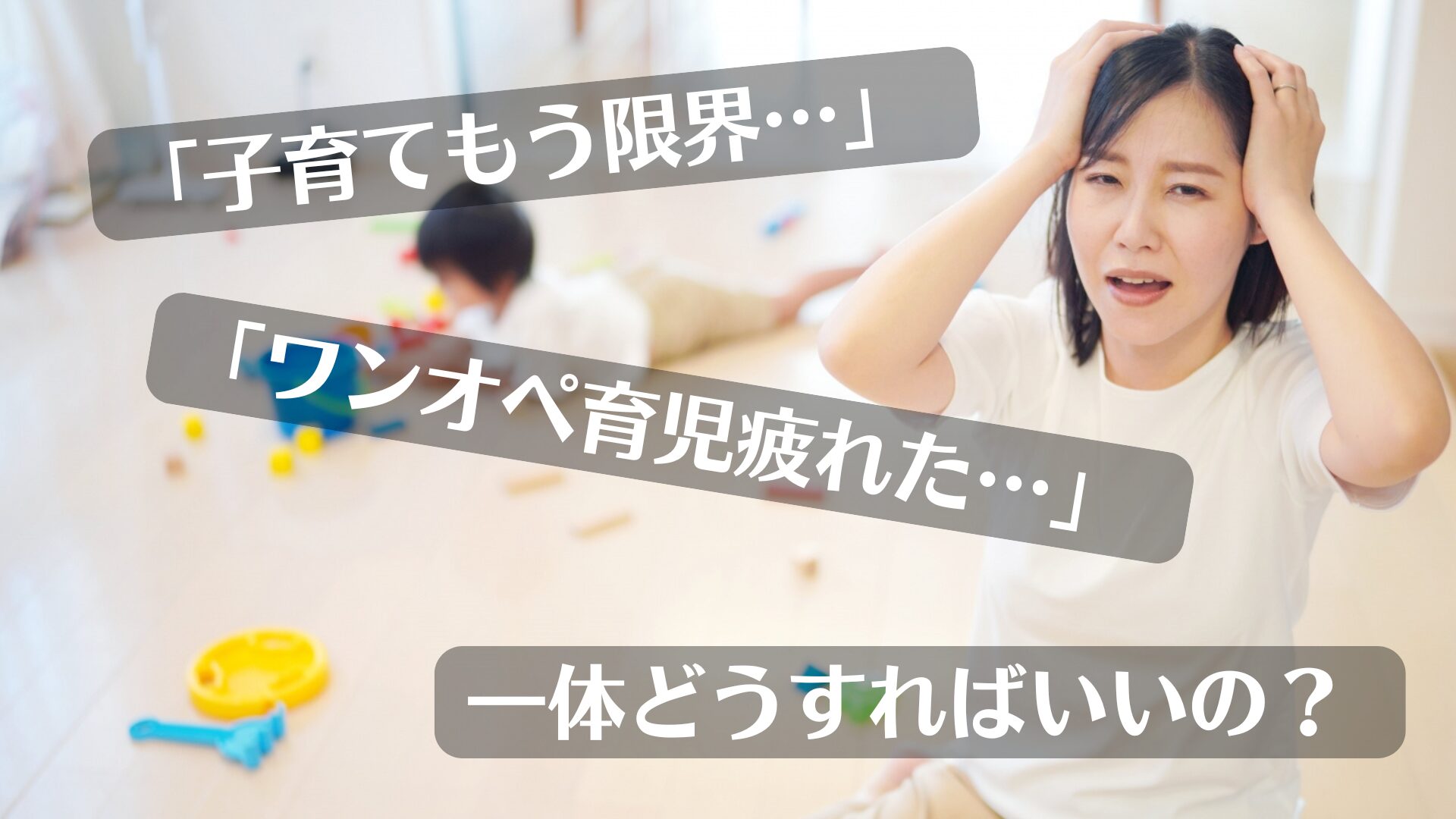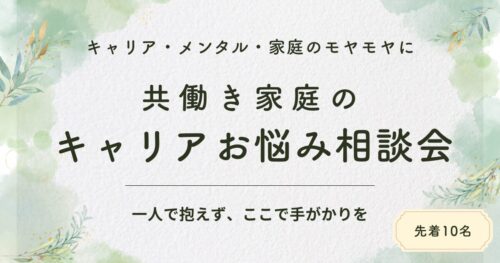共働き家庭では、仕事と家事や育児との両立が求められ、忙しい中でうまくできるかどうか、心配になるものです。
特に、ワンオペ状態が続くと「これって普通なの?」「みんなどうしてるの?」と、不安や孤独感も募っていきます。
私はキャリアコンサルタントとして、共働き家庭の相談を数多く受けてきましたが、ご家庭のお悩みで特に多いのが「家事育児と仕事の両立がつらい」「夫婦の価値観が違い過ぎる」というものです。
この記事では、6か月の男性育休、10年以上の家事育児経験を持つ二児のパパの立場から、育児や子育てが少しラクになるヒントをお届けします。よかったら参考にしてみてください。
なお、「すぐにでも相談をしたい」という方は、仕事と家庭の両立の問題を解決するためのキャリアカウンセリングを承っていますので、お気軽にご相談ください。
著者プロフィール
堀 左馬之介(ほり さまのすけ)。キャリアリカバー代表。国家資格キャリアコンサルタント(登録番号16062528)
企業・教育機関・医療機関を対象に、キャリアコンサルティングや研修を行うほか、
個人向けには、キャリアカウンセリングやキャリアプログラムを提供。
現在は心療内科クリニックや大学で「キャリアデザイン」の講師として活動、
東京都健康長寿医療センター研究所では、キャリアコンサルタントとして孤立・孤独の予防の研究に従事。
これまでに6,600回以上のキャリア相談と700回以上の研修・セミナーを実施。
男性育休6か月や家事育児10年以上の経験、自ら転職7回、ニート2年、事業縮小による解雇経験もあり、実体験に基づいたアプローチを得意としています。
ワンオペ状態を抜け出すための5つのポイント

「察して」は難しい。気持ちを言葉にして届ける
共働きで家事や育児を一生懸命こなしている人ほど、「実は限界かも…」という気持ちをうまく言葉にできず、ひとりで抱え込んでしまうことがあります。
でも、周りから見るとどうでしょうか?
いつも通り動けているように見えたり、「テキパキしてる」「ちゃんとやれてる」と思われたりして、「つらさ」が伝わっていないことが少なくありません。
そうして、頑張っている姿だけが見えると、なかなか声をかけてもらえないもの。
結果的に、心も体も少しずつ消耗していき、大きなダメージにつながることもあるのです。
「こんなに頑張ってるんだから、気づいてくれてもいいのに」そう思ってしまうのは当然。でも、言葉にしないと想いは届きにくいです。
また、周囲の人が「ちょっとつらそうかも」と感じていたとしても、「でも本人から何も言ってこないし」「こちらから手を出すのは余計かも」と、声をかけるのをためらってしまうこともよくあります。
そんなときは、勇気を出して「最近ちょっとつらくて…」「少し話を聞いてくれる?」と自分から伝えてみてください。
すると、意外にも「えっ、そうだったの? 全然そんなふうに見えなかった」「気になってたけど、声をかけづらくて…話してくれてよかった」という言葉が返ってくることがあります。
「察してもらう」より「伝えてみる」ことが、気持ちが楽になる第一歩になるのです。
自分と家族の安定を最優先に、夫婦で話し合う
家事や子育てに不安や負担を感じたとき、まず頼れる存在は一番身近なパートナーです。
しかし、共働き家庭の中には、収入が多い側ほど家事や子育てから距離を置いてしまうケースも少なくありません。
「仕方ない」と我慢して一人で抱え込んでいると、心身が疲れ果ててしまい、やがて仕事にも影響が出てしまうかもしれません。さらに、「どうしてもっと早く言ってくれなかったの?」後から責められることも。
そのようなことが続くと、世帯収入や夫婦関係にまで悪影響を及ぼす可能性もあります。
こうした事態を避けるためには、「このままだと体調を崩しそうで、仕事にも支障が出るかもしれなから、少し家事を手伝ってくれると助かるな」のように、パートナーの立場や視点を意識して伝えてみるといいかもしれません。
実際に私が受けたキャリア相談では、出産後の生活について夫と話し合ったことがなかったという妻の方が、「ワンオペ育児が当然」と思い込んでいたケースがありました。
しかし、後から夫に「実は育休を取りたかった」と打ち明けられたとのこと。
夫は育休制度について知識不足だったため、妻が早い段階で話し合っておけば、育休に関する法律や制度の知識について話し合うことができ、アクシデントを回避することができたかもしれません。
男女の視点は異なることが多いので、どのような小さなことでも、まずは話してみる、共有してみることが家族の安心につながります。
パートナー以外の人への相談や社会資源を活用する
とはいえ、夫婦間の話し合いだけではどうにもならないこともあります。
話し合いがすれ違いに終わったり、価値観の違いが浮き彫りになったりして、余計に疲れてしまうこともあるかもしれません。
そんなときは、気のおけない友人や先輩ママパパ、親などに相談してみましょう。身近な人の体験談には、きっとリアルなヒントが詰まっています。
もし、周囲に相談できる相手がいないとか、気を遣って話しづらいという場合には、公的な支援機関の利用もおすすめです。「子育て支援+地域名」で検索すると、地域の子育て支援センターや相談窓口の情報が見つかります。
たとえば、東京都であれば「東京都福祉保健局」のホームページからも、支援制度やサービスの一覧が確認できます。
「家庭の問題は家庭の中で解決しないと…」と思いがちですが、外部の力を借りることでヒントを得られることもたくさんあります。
子育てちゃんねるや育児ブログも参考にする
最近では、子育てにまつわる情報をブログやSNSで発信している人も多くいます。
「子育てちゃんねる」とか「育児ブログ」と検索すれば、リアルな体験談や便利グッズの紹介に出会えるかもしれません。
とくに、子どもの成長に応じて何をどれくらい準備すればいいか悩む方にとって、実体験をもとにした情報はとても役立ちます。
「子育てちゃんねる」とか「育児ブログ」などの体験談は、ご本人の具体的な体験をもとに書かれていることが多いです。その中から、自分のケースに近いエピソードを探すことで、具体的な解決策を見出すヒントにつながります。
家事代行サービスを活用する
共働きで子育てをしていると、平日は仕事、休日は子どもとの時間で一杯いっぱい。家事をする時間や体力が足りず、常に何かに追われているような気持ちになることも。
ハウスクリーニングやエアコンクリーニングはプロにおまかせ!【ユアマイスター】海外では、ハウスキーパーの利用が当たり前の国もありますが、日本ではまだ「特別なサービス」と感じる人も多いかもしれません。
でも、忙しい毎日を少しでも心地よくするための工夫として、季節の変わり目や年末の掃除時期などにスポット利用するのもおすすめです。
無理をして体調を崩してしまうくらいなら、外部のサービスを活用して、健康を保ったり、自分の時間を確保したほうが、長い目で見てもメリットが大きいかもしれません。
家事育児や子育てについて相談する3つのメリット

家事や育児、子育ての悩みを「誰かに相談する」ことには、大きな意味があります。
ここでは、共働き家庭の方や子育て中の方が相談することで得られる3つのメリットをご紹介します。
先輩ママパパや親から、経験に基づく「リアルな情報」が得られる
家事や育児に不安を感じたとき、すでにその道を通ってきた人の話には、教科書では得られないリアルなヒントが詰まっています。
先輩ママパパや親世代の経験談には、自分たちがこれから直面するかもしれない課題とその乗り越え方が凝縮されており、選択肢を増やす材料にもなります。
私自身も、自分の親に聞くのは少し気恥ずかしさがありましたが、ふとした一言に「あ、そういう考え方もあるんだ」と救われたことが何度もありました。自分の親に聞くのが恥ずかしい場合は、パートナーの親に話を聞いてみるのも一つです。
様々な人に聞いてみることで、それぞれ価値観に基づいたケースをたくさん知ることができ、客観的に判断できるようにもなります。
状況を伝えることで、思わぬ援助や手助けにつながる
援助をお願いするのは、少し抵抗があるかもしれません。私自身も、相手に気を遣わせたくない気持ちが先に立ち、つい遠慮してしまうことがあります。
そこでおすすめなのが「状況を共有する」という方法。
「いまこんな状況で」とか「こんなことで困っていて」と、率直に話すことで、思わぬサポートを受けられることもあります。
実際、私たち夫婦も親との何気ない会話から、子育てグッズやおむつなどを援助してもらったことがありました。何かと出費がかさむ時期だったので、本当に助かりました。
援助したいと思っている側にとっても、「何が困っているか」が分からなければ手を差し伸べにくいもの。伝え方を工夫することで、お互いにとって気持ちの良いコミュニケーションにつながります。
話すだけでも、心が少し軽くなることがある
子育てや家事の悩みは、必ずしもすぐに解決できるわけではありません。相手の家庭環境や価値観が自分と違えば、相談しても的確なアドバイスがもらえるとは限らないもの。それでも「誰かに話す」ことには大きな意味があります。
実際、私が受けたキャリア相談対応でも、相談者の方が「ただ話しただけなのに気持ちがラクになった」とおっしゃることは多くあります。
誰かに話を聞いてもらい、気持ちを整理し、共感してもらうだけでも、ストレスの軽減や気持ちの安定につながることがあるのです。
このように、話すことで心がスッキリすることを「カタルシス効果」と呼びます。答えが出なくても、思いを口にするだけで、少し前向きな気持ちになれることもあるでしょう。
身近な家族や友人に相談するのもよいですし、公的機関や、私が関わっている「家事育児とキャリアの両立支援」を行うキャリアカウンセリングなど、第三者の力を借りる選択肢もあります。
「こんなこと話していいのかな?」とためらう必要はありません。話すことで見えてくる答えも、きっとあるはずです。
相談することは「負け」ではなく、むしろスキル

相談という行動は「自分一人で解決できないダメな人」と思われてしまうなど、マイナスなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
しかし、相談することは決してダメなことではありません。
仕事にも報連相とあるように、相談という行動はチームプレイには欠かせないもので、問題解決のためのスキルでもあります。
一人で悩みを抱えず身近な人や支援機関に相談することで、家族というチームを安定させるとともに、家事育児や子育てスキルの向上にもつながります。
「相談はメリットがたくさん」と受け止めて一歩踏み出せるようになると、違った世界が見えてきます。
まとめ
- 共働きが当たり前の時代。家事育児は夫婦の「チームプレイ」
- 一人で悩まず、体調を崩す前にまずは身近な人に相談する
- 情報は「自分の中だけ」ではなく、外から集めてヒントに
- 支援機関や専門家への相談も、有益な選択肢のひとつ
- 「相談することは負けではなく、問題解決スキル」
本記事を執筆したキャリアリカバーでは、心療内科クリニック講師、6か月の男性育休の経験を持つ国家資格キャリアコンサルタントが、共働き家庭のキャリア形成・育児の悩み・メンタルの不安に、まるごと寄り添ったサポートを提供しています。
あなたの「これから」を一緒に考えるお手伝いができたら嬉しいです。